先日ある社長さんからこんな質問をいただきました。
「今3人の会社で、自分が会社のほとんど全てを回してますが、もう手一杯です…。事業を拡大したいと思っていて、人を増やさなきゃって思っているんですが…、今の規模から年商1億を目指すのに、従業員は何人くらいがちょうどいいんでしょうね?」とのこと。
その方には、その方の業種で最適な数字をお答えしましたが…
- 自分は従業員を抱えすぎなのでは?
- 事業を伸ばしていきたいけど、何人までなら大丈夫?
- 今の手一杯の状況がいつまで続くのか?
こういった疑問は、多くの経営者さんが人知れず不安に思っていて、誰にも相談できずに悩みを抱えている、難しい問題だったりします。
実際こういった不安はとても真っ当で、中小企業の経営が傾く大きな原因が「売上と見合わない数の従業員を雇いすぎ」…ようは、人件費によってお金が足りなくなり、赤字経営に陥るケースが少なくありません。
そこで今回は、年商800万円から年商500億を超える上場会社の役員まで、累計35業種のビジネスの財務顧問を務めるビジネスパートナーに聞いてみました。「年商1億の会社の従業員数は何人が最適なのか?」正解ではなくても「安全・安心」の状態をつくれる答えらしきものを記事にしたいと思います。
厳密に言えば「業種によって違います」が答えになってしまいます。
ただ、できる限り業種に関わらず使える判断の目安を示してみたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。
年商1億企業の最適な従業員数は…?
もったいぶらずに結論から言うと…
「ひとり当たりの粗利額が1000万円以上」
になるようにするとひとまず安心
というのが、私たちの考えです。
よくこの手の議論で「従業員1人当たり売上2,000万円以上が優良企業」という風な説が聞こえてくることがありますが、やはり売上を基準にすると業種によるバラつきがとっても大きくなってしまいます。
例えば…建設業と整体院とでは、仕入れも材料費も利益率、全く違いますからね。
こういった商品をつくるのに直接必要な「原価」を差し引いた額の「粗利」を基準にした方が、実態にあった数字を出しやすいです。
実際の事例を使って解説

例えば、製造業を営んでいる年商1億円ほどの社長さんを例に考えてみましょう。
製造業の原価率(仕入れにかかる費用や材料費等)は、35%〜50%が相場(販路によって異なりますが…)。そうすると1億円の売上をつくるのに3500万円〜5000万円の原価がかかります。
※ ここでは「労務費と人件費との違い」といった会計ルールの細かい部分は割愛しています。純粋に商品をつくるのにかかる費用で「人にかかる費用でないもの」を「原価」。売上高から「原価」を引いたものを「粗利」として考えます(厳密に考えようとすると難しいですからね…こちらの方が会計ルールより実態に合ってると思います)。
とすると…粗利額は5000万円〜6500万円。
「ひとり当たりの粗利額が1000万円以上」を意識すると(粗利1000万円で割ると)社長含め社員は5人〜6人ほどが適切。従業員数で考えると、社長を除いて4人か5人ほどが安全・安心な数…ということになります。
年商2億を目指すのであれば、原価が1億円〜1億3000万円。
粗利が7000万円〜1億円になるので、社長を除き6〜9人ほどがひとまず安心な従業員数ということになります。
パートやアルバイトというカタチで…
この数字以上に従業員を抱えているケースももちろんありますが、正直シンドいです…。
粗利から広告費や諸々の販売費、そのほかの一般管理費が出て行ってしまいますからね。さらに、従業員の給料は毎月固定費として出て行きます。すると、よほどキャッシュに余裕がない限り、突発的なトラブルで苦しい状態に追い込まれてしまうこともままあります。
この計算方法であれば、売上規模に応じた従業員数を割り出せるので、実際にあなたご自身のビジネスで、原価率も算出してみて、計算してみてください。
こういった情報は知っておくだけで、現状を正しく理解するのに役立ちます。現状を理解しているだけで漠然とした不安を抱えずに済みますからね。
業種別:年商規模の高め方
ちなみに…
従業員数の増加は、固定費の増加。
売上ベースの確保と安定化が欠かせません。
そこで、これまでの支援実績や事例をもとに業種別の年商規模の高め方をまとめてみました。
情報系・専門技術職のための 売上拡大策3選
コンサルタントやデザイナー、マーケター、士業などの情報系・専門技術系の事業 を営む社長が、従業員を増やすにあたり売上拡大が必要!というのであればコチラ。年商1億につながりやすくなる売上拡大施策をまとめました。
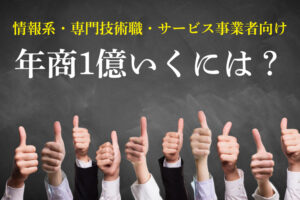
店舗ビジネス事業者のための売上安定&拡大策3選
カフェや、クリニック、美容室やハウスクリーニング、歯科医や動物病院など。店舗ビジネスを営む事業者さんで従業員を増やすにあたり、売上のベースアップや安定化が必要!というのであればコチラ。再現性が高く、効果実証済みの売上拡大のための集客手法をまとめています。









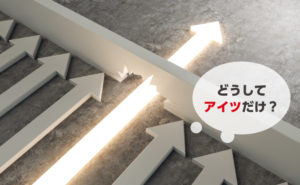
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 年商1億の会社の従業員数…何人が最適? […]